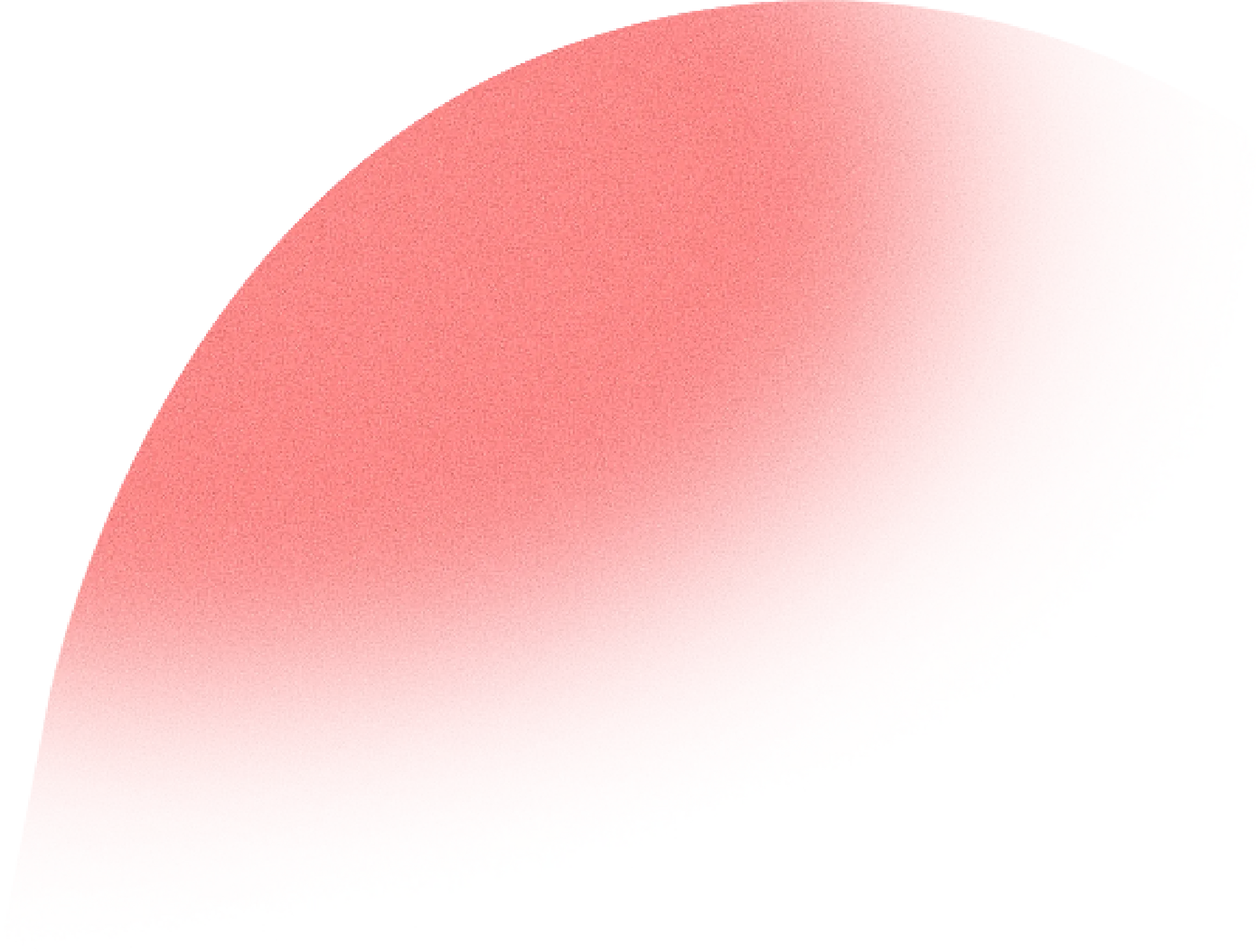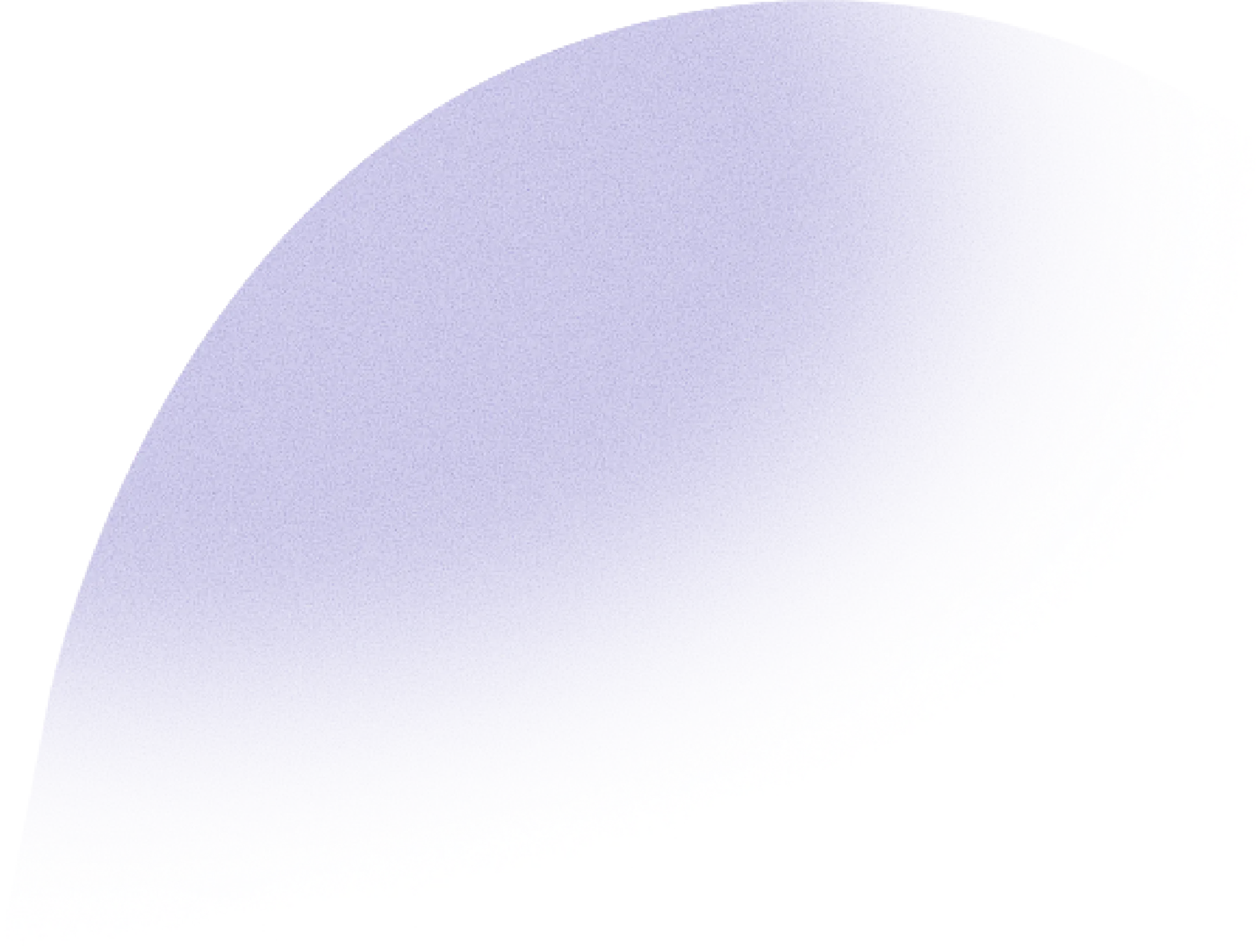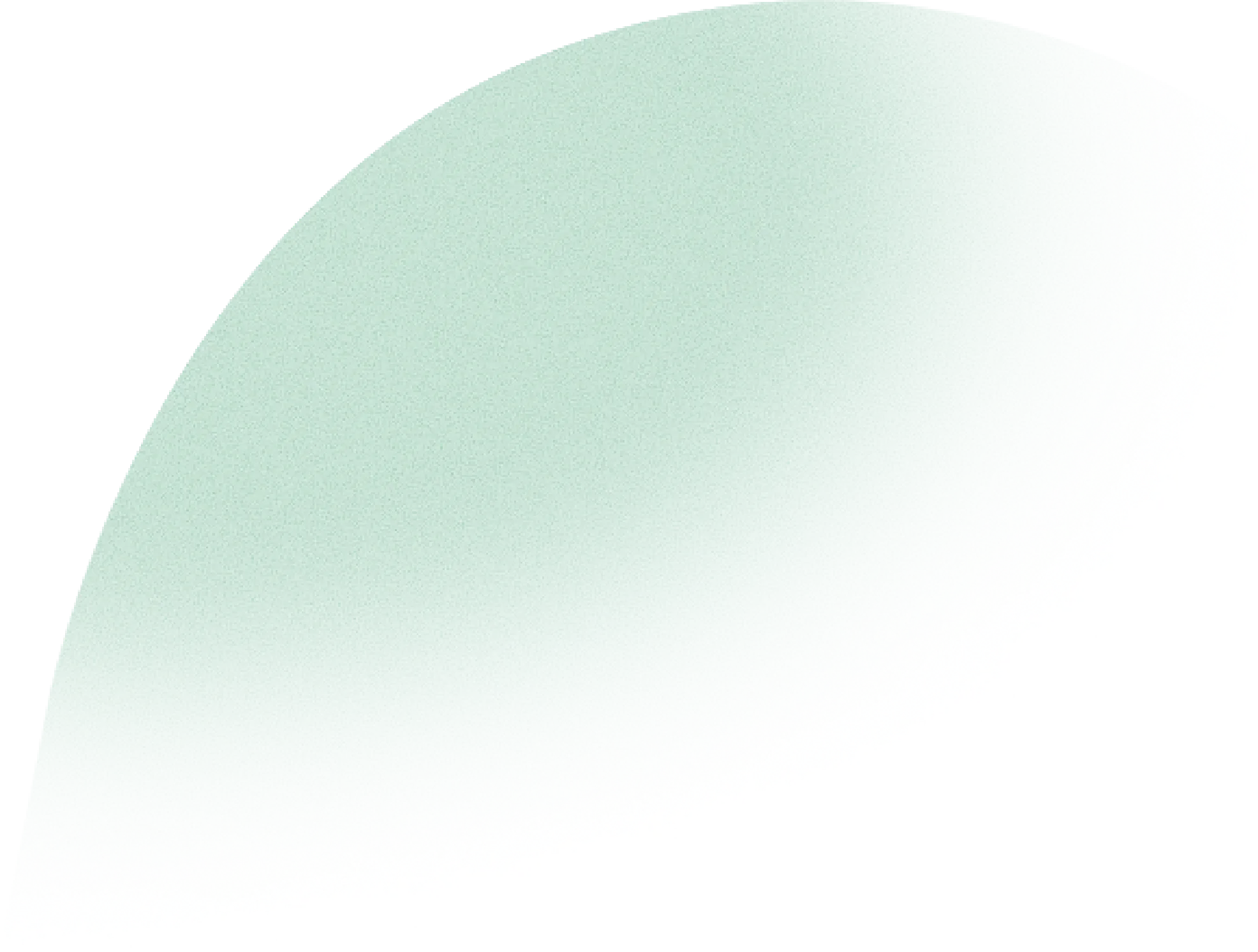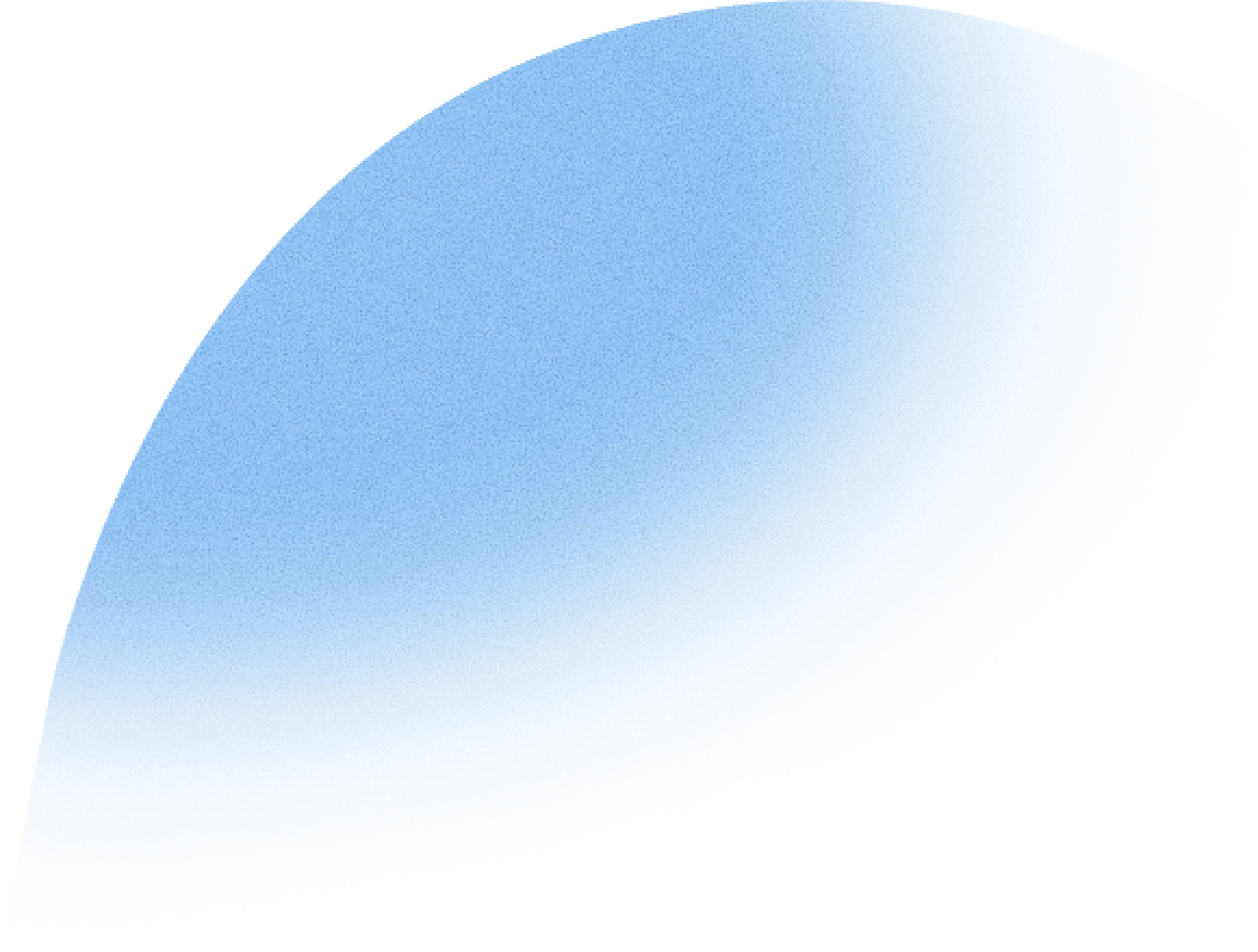きものの装いにおいて、衿元のおしゃれはお顔まわりの印象を大きく左右します。
衿の色やデザインが違うだけで、華やかさが増したり、落ち着いた雰囲気になったりと、コーディネートの幅が一段と広がるでしょう。
とくに刺繍衿や伊達衿は、フォーマルな場面やお祝いの席で活躍し、きものの装いに華やかさを添えてくれるのです。
本記事では、半衿と伊達衿の違いや、それぞれの役割、正しいマナーや色合わせのコツについて詳しく解説します。

半衿と伊達衿の違い
きものの衿元には、きものを汚れから守る役割がある「半衿(はんえり)」や、華やかさを演出する「伊達衿(だてえり)」などの小物を使用します。
それぞれ異なる役割を持ち、着こなしやシーンに応じて適切に選ぶことが重要です。
半衿とは?特徴と役割
半衿は長襦袢につける衿のことで、汗や化粧で衿が汚れるのを防ぐ役割があります。
また、顔映りをよくする効果もあり、白や淡い色の半衿は明るく上品な印象を与えてくれるでしょう。
さらに、半衿と地衿の間に衿芯を通すことで、衿元をしっかりと固定し、着付けを美しく仕上げる効果もあります。

半衿の種類
半衿の素材やデザインには、さまざまな種類があります。
- 白衿 :王道の衿。礼装用などフォーマルな場面でも安心して使用できる
- 色付き衿:きものや帯との色合わせで個性的なコーディネートが楽しめる
- 刺繍衿 :華やかな柄の刺繍が施され、振袖などの晴れ着に適している
伊達衿とは?特徴と役割
伊達衿(だてえり)は重ね衿とも呼ばれ、きものを二枚重ねで着ているかのように見せるための衿のことです。
とくに、華やかで格式ある装いを演出するためのアクセントとして、振袖や訪問着などに用いられます。
平安時代の女房装束(十二単)に見られる襲色目(かさねいろめ)の美しさが、現代のきものにも受け継がれているのです。

伊達衿の付け方
伊達衿の寸法は幅10.5cm・丈120cm前後が一般的で、きものの衿に “衿ピン” や “縫い糸” で固定します。
きものの衿から伊達衿が数ミリ見えるようにズラし、衿の中央とその左右約10cmのところを留めましょう。
華やかさを演出する「伊達衿」を合わせるきもの
伊達衿は、礼装やお祝い事の際に使用されることが多く、「喜びを重ねる」という縁起のいい意味があります。
【伊達衿を合わせやすいきものの種類】
- 振袖:成人式や結婚式の参列など華やかな場面に最適
- 訪問着:フォーマルな場面で格式を高められる
- 色無地:シンプルながらもおしゃれな装いに活用
- 付け下げ:控えめな華やかさを演出
- 小紋:カジュアルな着こなしのアクセントとなる
ただし、留袖には比翼があるため、伊達衿は不要とされています。
また、「重なる」という意味合いから、喪服には使用しません。
振袖に合わせる伊達衿
振袖は、成人式や結婚式の披露宴など、華やかな場で着用される格式の高いきものです。刺繍衿や華やかな色合いの伊達衿を選ぶことで、より豪華な印象になります。
振袖に合わせる衿は、金や銀の刺繍が施されたものや、赤・ピンク・緑など鮮やかな伊達衿が人気です。
振袖の柄や帯とのバランスを考えながら、アクセントとして映える色を選ぶといいでしょう。
訪問着・色無地・付け下げに合わせる伊達衿
訪問着・色無地・付け下げは、主にセミフォーマルな場面で活躍するきものです。刺繍衿や伊達衿を加えることで、落ち着いた雰囲気の中にも華やかさを添えることができます。
とくに、控えめながらも品のある色合いの伊達衿を採用することで、きものの格式を高めることができるでしょう。
例えば、きものの地色に近い同系色の伊達衿を選ぶと落ち着いた印象になり、金や銀の縁取りが入ったものを選べば、控えめな華やかさを演出できます。
小紋に合わせる伊達衿
小紋は、カジュアルなシーンやおしゃれ着としても楽しめるきものですが、刺繍衿や伊達衿を合わせることで、ワンランク上の着こなしを実現できます。
小紋に合わせる場合は、遊び心のあるデザインや、個性的な色使いを選ぶのがおすすめです。
また、季節感を意識した色を選ぶと、洗練されたおしゃれを楽しむことができます。
桜の季節にはピンクや薄紫、秋には深緑やワインレッドなどが映えるでしょう。
悩まない伊達衿の色選びのコツ
伊達衿の色選びは、きもの全体のバランスを取る上で重要なポイントです。
以下のポイントを参考にするとバランスよくまとまります。
【色選びのコツ】
- きものの地色の濃淡
- きものの柄の中の一色
- 華やかな色
- 趣味的な淡い色
- きものの裾まわしと共色
- 帯と同系色
- 帯揚げや帯締めの色
きものの地色の濃淡を意識したり、きものの柄と同じ色味を選んだりすることで、コーディネート全体の統一感が生まれます。
また華やかさを演出したい場合は、ゴールドやシルバー、赤、ピンクなどの明るい色を選ぶと効果的です。
伝統的な色合わせとして、きものの裾まわしと同じ色を使う方法もあります。
まとめ
刺繍衿や伊達衿を取り入れることで、きものの装いに華やかさを加えることができます。
とくに、伊達衿は格式あるシーンでの着こなしを引き立て、衿元の印象をより一層美しく演出するアイテムです。
当学院では、きものの着付けだけでなく、色彩の勉強も行っています。
伊達衿などの小物を活用する際には、色の組み合わせによる印象の違いを理解し、自分に似合うコーディネートを楽しむことが大切です。
色彩の知識を深めながら、きものの装いをより素敵に演出しましょう。